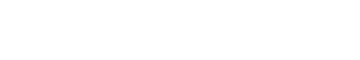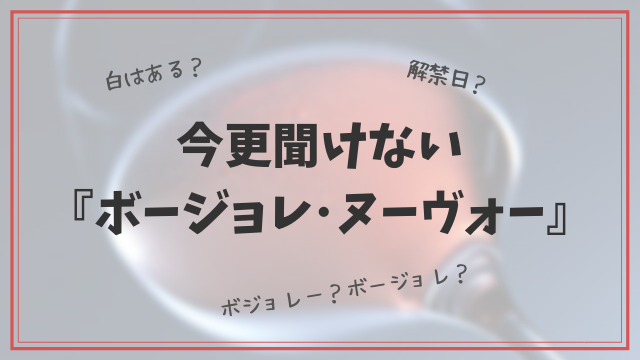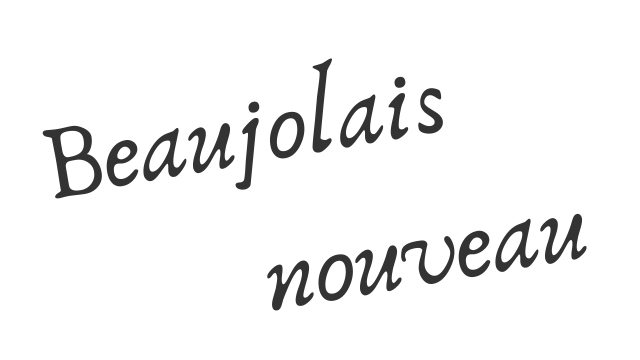秋になり、今年も各社ボージョレの販売情報が集まってきました。
「…けど、そもそもボージョレ・ヌーヴォーって何??」
「なんかアレでしょ、解禁されるワイン」
「ボージョレ?ボジョレー?ヌーヴォ?ヌーボー?」
と思ってる方も実はいるのではないでしょうか!
恥ずかしがらなくて大丈夫です。
そんな方のために、ボージョレ・ヌーヴォーって一体何?ということをまとめました。
この記事を読むと分かること
- そもそもボージョレ?ボジョレー?
- ボージョレってそもそも何?なんで『解禁』?
- ボージョレって赤だけ?白はあるの?
そもそもボージョレ?ボジョレー?
ボージョレ・ヌーヴォーをフランス語で書くと『Beaujolais nouveau』。
Beaujolaisはフランスの『ボージョレ地区』つまり、地名です。
nouveauは『新しい』という意味、転じて『新酒』の意味です。
では肝心の発音は…というと、実は『ボジョレーヌーヴォー』の方が近いです。
お使いの端末にもよりますが、上記から発音が確認できるかと思いますので聞いてみてください。
フランス語・英語共に、音としては『ボジョレー』に近いはずです。
(ただ、日本語訳した時のカタカナは『ボージョレ』表記)
実は日本の慣例として以下のように使い分けがされています。(例外あり)
- テレビ各社:原則『ボジョレー』で統一
- 新聞各社:原則『ボージョレ』で統一
そのため、別にどちらでも間違っていないのです。
ただ、日本のワイン業界では『ボージョレ』の表記が比較的多く使われています。
そのため当サイトでも原則として『ボージョレ』の表記を使うこととしています。
(引用元や固有名詞として『ボジョレー』が使われる場合はそのまま使用しています。)
ボージョレ・ヌーヴォーってなに?
言葉の意味の通り、ずばり『フランスのボージョレ地区で造られるその年の新酒ワイン』のことです。
ボージョレ地区はブルゴーニュ地方にあり、元々はその年のブルゴーニュワインの出来を予想するために業界関係者の間で消費されていました。(諸説あり)
更に遡ると、農民たちが収穫祝いのワインとして作ったのが発祥と言われています。(こちらも諸説あり)
しかし、いつしかそれが一般の消費者に広まり、段々とお祝い事のように商業イベントになっていったのです。
こんなことを書くと「日本人はミーハーだからイベントごとに弱い」と言われがちですが、今ではボージョレの解禁は世界中で楽しまれるイベントになっています。
ただし、元々はブドウの出来を見るための『試飲酒』です。
そのためワインとしては長期熟成に耐えられず、数ヶ月以内に飲みきることを前提とした造りになっています。
解禁日は11月の第3木曜日
ボージョレ・ヌーヴォーには、発売の『解禁日』が定められています。
これは、『一日でも早く発売した方が売れ行きがいい』という理由で不完全な状態で出荷する業者が出てきたため、品質を保つために設けられたものです。
現在の解禁日は、発売される国の現地時間で11月第3木曜日(の午前0時)です。
(元々は11月11日でしたが、物流の都合などもあり11月11日→15日→第3木曜日と変更されていきました。)
- 2019年:11月21日
- 2020年:11月19日
- 2021年:11月18日
- 2022年:11月17日
- 2023年:11月16日
2019年の解禁日は、11月21日。
2019年11月1日が金曜日なので、最も遅い解禁日ですね。
解禁は『発売される国の現地時間』なので、時差の関係上日本は世界でもかなり早い時間に解禁されることになります。
解禁日を定めているのはあくまでのフランスの法律なので、日本で解禁日を破っても罰則はありません。
そのため、一部の悪質な店舗では解禁日前のフライング販売をしていることもあります。
生産者のことや、解禁日に間に合うように税関の特別措置で事前通税されていることを考えると、このような店は淘汰されるべきだと思います。
ボージョレ・ヌーヴォーの作り方
ボージョレ・ヌーヴォーは夏に収穫したブドウを11月下旬の解禁日に世界各国に届けるために、短期間で醸造する特別な作り方をします。
使われるブドウは、ガメ種(ガメイ種)と言われる品種。
タンニンが少なく、長期熟成には向かないためデイリーワインなどに使われる品種です。
実際には、ボージョレ・ヌーヴォー以外ではあまり見かけないかもしれません。
醸造はMC法(マセラシオン・カルボニック)と呼ばれる、炭酸ガスを充満させたタンク内で発酵させる方法で造られます。
この発酵方法により、ボージョレ・ヌーヴォー独特のバナナのような香りが形成されます。
ワンランク上のAOC『ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー』
ボージョレ・ヌーヴォーの中でも、北部にある38の村(ヴィラージュ)で生産されたものを『ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー』と呼びます。
ボージョレ地区の中でも特に良質なワインを造り、通常のボージョレ・ヌーヴォよりも芳醇な香りを楽しめます。
「美味しいボージョレが飲みたいな~」と思ったら、『ヴィラージュ』と付いたものを探してみるといいかもしれません。
毎年恒例の『キャッチコピー』問題
繰返しになりますが、現代のボージョレ・ヌーヴォーは『商業イベント』としての側面が色濃いものとなっています。
そのため、輸入業者や販売業者がこぞって『今年は最高!』といったコピーを打ち出すのがもはや風物詩となっています。
販売業者らの評価
1983年「これまでで一番強くかつ攻撃的な味」
1985年「近年にない上物」
1992年「過去2年のものよりフルーティーで、軽い」
1995年「ここ数年で一番出来が良い」
1996年「10年に1度の逸品」
1997年「まろやかで濃厚。近年まれにみるワインの出来で過去10年間でトップクラス」
1998年「例年のようにおいしく、フレッシュな口当たり」
1999年「1000年代最後の新酒ワインは近年にない出来」
2000年「今世紀最後の新酒ワインは色鮮やか、甘みがある味」
2001年「ここ10年で最もいい出来栄え」
2002年「過去10年で最高と言われた01年を上回る出来栄えで1995年以来の出来」
2003年「110年ぶりの当たり年」
2004年「香りが強く中々の出来栄え」
2005年「タフな03年とはまた違い、本来の軽さを備え、これぞ『ザ・ヌーボー』」
2006年「今も語り継がれる76年や05年に近い出来」
2007年「柔らかく果実味豊かで上質な味わい」
2008年「豊かな果実味と程よい酸味が調和した味」
2009年「過去最高と言われた05年に匹敵する50年に一度の出来」
2010年「2009年と同等の出来」
2011年「100年に1度の出来とされた03年を超す21世紀最高の出来栄え」
2012年「偉大な繊細さと複雑な香りを持ち合わせ、心地よく、よく熟すことができて健全」
2013年「みずみずしさが感じられる素晴らしい品質」
2014年「太陽に恵まれ、グラスに注ぐとラズベリーのような香りがあふれる、果実味豊かな味わい」
2015年「過去にグレートヴィンテージと言われた2009年を思い起こさせます」
出典:Wikipedia
一体、何回最高を更新してるんだ…って感じですね。
実はこれとは別に、現地のボージョレワイン委員会が比較的控えめな品質予想を出しています。
ボジョレーワイン委員会の品質予想
2002年「色付きが良く、しっかりとしたボディ」
2003年「並外れて素晴らしい年」
2004年「生産者の実力が表れる年」
2005年「59年や64年、76年のように偉大な年の一つ」
2006年「とてもうまくいった年」
2007年「果実味が豊かでエレガント」
2008年「フルーツ、フルーツ、フルーツ」
2009年「数量は少なく、完璧な品質。桁外れに素晴らしい年」
2010年「果実味豊かで、滑らかでバランスの取れた」
2011年「3年連続で、偉大な品質となった」
2012年「心地よく、偉大な繊細さと複雑味のある香りを持ち合わせた」
2013年「繊細でしっかりとした骨格。美しく複雑なアロマ」
2014年「エレガントで味わい深く、とてもバランスがよい」
2015年「記憶に残る素晴らしい出来栄え」
2016年「エレガントで、魅惑的なワイン」
出典:Wikipedia
これを見ると、本当に『当たり年』と言えるのは2003年、2005年、2009年、2010年、2011年、2015年といったところでしょうか。
白のボージョレ・ヌーヴォーはある?
ボージョレを名乗れるワインは、赤はガメイ種・白はシャルドネ種を100%使用しなくてはいけません。
とはいえ実際はその約99%が赤ワインで、白のボージョレは約1%しか生産されていません。
しかしこれはヌーヴォーだけでなく、ボージョレワイン全体の割合。
ボージョレ・ヌーヴォーの場合はガメイ種100%の赤ワインと定められています。
つまり、白のボージョレ・ヌーヴォーは存在しないのです。
しかし、ボージョレ地区の隣『マコン地区』では、シャルドネを使った白ワインの新酒が造られています。
その名も『マコン・ヴィラージュ・ヌーヴォー』。
ボージョレ―よりも知名度が低いのであまり一般的ではありませんが、ボージョレとマコン、2種のヌーヴォー飲み比べも楽しいかもしれませんね。
まとめ
- ボージョレ・ヌーヴォーは元々『ブドウの出来を測るための試飲酒』
- 商業イベントとして、11月第3木曜日(2019年は11/21)の解禁を祝うようになった
- ボージョレ・ヌーヴォーは全て赤だが、白のヌーヴォー『マコン・ヴィラージュ・ヌーヴォー』がある
こんなことを知っていると、普段スルーしているイベントも楽しめるのではないでしょうか!